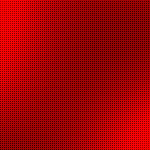「新潟のすごさって、何ですかね」。
ふと、そんな問いを投げかけられることがあります。
きらびやかな観光名所も、もちろん素晴らしい。
でも、わたくし小山内理沙が長年この土地で記者として見つめてきたのは、もっと日々の暮らしに根ざした、いわば“普通”の風景なんです。
生まれ育った十日町の雪深い里山、そして今暮らす新潟市の賑わい。
そのどちらにも、当たり前のように息づく知恵や文化があります。
それは、派手さはないかもしれねぇけど、実はものすごく豊かで、力強いものなんですよ。
この記事では、そんな新潟の「普通」のなかに隠された「すごさ」を、わたくしの視点から紐解いていきたいと思っています。
雪国の暮らし、豊かな食、そしてそこに生きる人々の声。
一緒に、新潟らしさの再発見に出かけてみませんか。
きっと、あなたの知らない新潟の魅力に出会えるはずです。
目次
雪国の暮らしが育む“当たり前”の底力
新潟の冬といえば、なんといっても雪。
わたくしが子どもの頃は、一晩で背丈ほども積もるなんてことは、ざらでした。
この厳しい自然環境が、新潟の人々の暮らしに独特の知恵と文化を育んできたんです。
それは、決して特別なことではなく、日々の“当たり前”として受け継がれてきた底力なんですよ。
雪掘りとともにある生活の知恵
「雪掘りしないと、家から出られねぇ」。
これは、雪国に暮らす者にとって、冬の日常会話です。
朝起きればまず、玄関先や通路の雪を片付けることから一日が始まります。
屋根の雪下ろしも、放っておけば家が潰れてしまうから、命がけの作業でした。
「昔は、近所総出で助け合って雪下ろしをしたもんだよ。若い衆が屋根に上がって、下では女衆が雪を運んでね。あれはあれで、冬の一大行事だったな」
と、先日取材した魚沼のお年寄りが話してくれました。
雁木(がんぎ)なんていうのも、雪国ならではの知恵の結晶ですね。
家の軒先を長く出して通路を作ることで、雪が積もっても人々が往来できるようにしたんです。
あれがあるおかげで、冬でも町を歩けるんだから、たいしたもんです。
冬の家仕事と手しごとの文化
長い冬、外での仕事ができない間、家の中で行う「家仕事」もまた、新潟の暮らしには欠かせないものでした。
特に、わたくしの故郷・十日町周辺では、機織り(はたおり)が盛んでしたね。
雪に閉ざされる静かな時間の中で、女性たちは黙々と布を織り、それが小千谷縮(おぢやちぢみ)や十日町絣(とおかまちがすり)といった素晴らしい織物を生み出してきたんです。
他にも、ワラ細工やスゲ細工、竹細工など、身近な材料を使った手仕事がたくさんありました。
これらは、単なる暇つぶしなんかじゃありません。
厳しい冬を乗り越えるための生活の糧であり、同時に、美しいものを生み出す喜びや、手仕事の技を次の世代に伝えるという大切な役割も担っていたんです。
<雪国で育まれた手仕事の例>
- 織物: 小千谷縮、越後上布、十日町絣、十日町明石ちぢみ
- 編み物: 猫ちぐら(ワラ)、バテンレース
- 細工物: ワラ細工、スゲ細工、チンコロ(米粉細工)
これらの手仕事は、今もなお新潟の文化として大切に受け継がれています。
囲炉裏とこたつがつなぐ家族の記憶
冬の寒い夜、家族みんなで囲炉裏(いろり)を囲んだり、こたつに入ったりする光景は、雪国の原風景とも言えるでしょう。
囲炉裏の火は暖を取るだけでなく、煮炊きをしたり、部屋を乾燥させたり、さらには家の柱や梁を煙で燻して長持ちさせる役割もありました。
こたつに入って、おじいちゃんやおばあちゃんから昔話を聞いたり、家族で鍋をつついたり。
そんな何気ない日常の積み重ねが、家族の絆を深めてきたんだと思います。
火の温もりと、人の温もり。
それが、雪国の厳しい冬を乗り越えるための、大きな支えだったんでしょうね。
今では囲炉裏のある家も少なくなりましたが、あの温かさは、今もわたくしの心の中にしっかりと残っています。
食文化に宿る新潟のアイデンティティ
新潟といえば、やっぱり「食」の豊かさを語らずにはいられません。
米どころとして知られていますし、日本海の海の幸、山の幸にも恵まれています。
でも、新潟の食のすごさは、それだけじゃないんです。
厳しい自然環境の中で培われてきた保存の知恵や、季節の恵みを余すところなくいただく工夫。
そこにこそ、新潟の食文化の真髄、アイデンティティが宿っていると、わたくしは思うんです。
発酵が生きる——郷土の味と保存食の知恵
雪国新潟では、冬の間の食料を確保するために、保存食の文化が非常に発達しました。
その代表格が、発酵食品です。
1. 味噌・醤油
各家庭で味噌を仕込むのは当たり前の光景でした。
「手前味噌」という言葉があるように、それぞれの家の味があるんです。
わたくしの実家でも、毎年大きな樽で味噌を仕込んでいましたね。
2. 漬物
野菜が採れない冬のために、様々な漬物が作られました。
野沢菜漬け、大根の味噌漬け、粕漬けなど、種類も豊富です。
雪の下で甘みを増した野菜を漬け込む知恵は、まさに雪国ならでは。
3. かんずり
妙高市特産の「かんずり」は、唐辛子を雪の上に晒してアクを抜き、麹や柚子などと混ぜて発酵させた調味料です。
あの独特の辛味と風味は、鍋物や料理のアクセントに欠かせません。
他にも、魚と米を発酵させた「飯寿司(いずし)」や、納豆に刻んだ野菜を混ぜる「きりざい」など、地域ごとに特色ある発酵食が今も受け継がれています。
これらは、単に食べ物を長持ちさせるだけでなく、発酵によって旨味や栄養価を高めるという、先人の素晴らしい知恵の結晶なんです。
地元野菜と米のちから:四季を映す食卓
新潟は、言わずと知れた米どころ。
特に魚沼産コシヒカリの美味しさは、全国的にも有名ですね。
あのつやつやとした炊き立てのご飯は、何よりのご馳走です。
でも、お米だけじゃないんですよ。
春には香り高い山菜、夏にはみずみずしい夏野菜、秋にはきのこや根菜類、そして冬には雪の下で甘みを蓄えた冬野菜。
四季折々の地元野菜が、新潟の食卓を彩ります。
| 季節 | 代表的な地元野菜・食材 |
|---|---|
| 春 | 山菜(ふきのとう、こごみ、たらの芽) |
| 夏 | 十全なす、枝豆、きゅうり |
| 秋 | 里芋(帛乙女)、きのこ類、新米 |
| 冬 | 女池菜、大根、白菜 |
これらの野菜をたっぷり使った煮物や汁物、和え物などが、新潟の家庭料理の基本です。
例えば、代表的な郷土料理「のっぺ」は、里芋や人参、こんにゃく、きのこなどを煮込んだ、とろみのある優しい味わいの料理。
それぞれの家庭で入れる具材や味付けが少しずつ違っていて、まさに「おふくろの味」なんです。
季節の恵みを大切にいただき、その持ち味を活かす。
そんな食のあり方が、新潟には根付いています。
食とともにある祭りと年中行事
新潟の食文化は、地域の祭りや年中行事とも深く結びついています。
お正月には、家族や親戚が集まって「のっぺ」や「くじら汁」を食べるのが習わしでした。
田植えが終わった後には、朴葉にご飯ときな粉を包んだ「朴の葉まんま」を食べる地域もあります。
十日町雪まつりのような大きなお祭りでは、地元の食材を使った屋台がたくさん出て、賑わいますね。
また、冬の農閑期に行われる「節季市(せっきいち)」では、手作りの保存食や餅、チンコロなどが売られ、地元の人々の楽しみの一つでした。
食を通じて、人々が集い、交流し、地域の絆を深めていく。
そんな温かい文化が、新潟には息づいているんです。
U・Iターン者が語る“新潟の普通”の新鮮さ
最近、新潟県外から移り住んでくるU・Iターンの方が増えていると聞きます。
わたくしも、そういった方々にお話を聞く機会が何度かありました。
彼らが語る新潟の魅力は、私たち地元民が「当たり前」と思っていることの中にこそ、たくさん隠されているように感じるんです。
外から見えてくる新潟の魅力とは?
「東京にいた頃は、こんなに空が広いなんて気づかなかった」。
そう話してくれたのは、数年前に新潟市に移住してきた若いデザイナーさんでした。
毎日時間に追われる生活から離れ、新潟のゆったりとした時間の中で、自然の美しさや季節の移ろいを肌で感じられることが、何より新鮮だと言います。
他にも、U・Iターンの方々からは、こんな声が聞かれます。
- 食べ物がとにかく美味しい。 特に米と魚、そして野菜の味の濃さに驚くそうです。
- 自然が身近にある。 少し車を走らせれば、海も山もあって、気軽にアウトドアを楽しめる。
- 子育て環境が良い。 待機児童が少ない地域もあり、公園なども多く、のびのびと子育てができる。
- 人が温かい。 最初は少しとっつきにくいと感じることもあるけれど、一度打ち解けると親身になってくれる人が多い。
私たちにとっては見慣れた風景や日常が、外から来た人たちの目には、かけがえのない魅力として映る。
その事実に、ハッとさせられることがあります。
対話を通じて再発見される「らしさ」
U・Iターンの方々と話していると、私たち自身も「新潟らしさ」とは何かを改めて考えるきっかけになります。
例えば、雪国の「不便さ」。
冬の雪かきは大変だし、交通が麻痺することもあります。
でも、ある移住者の方はこう言いました。
「不便だからこそ、工夫するし、助け合う。それが人間らしい暮らしなんじゃないかと思うんです」
この言葉を聞いたとき、ああ、そうだな、と。
私たちは、厳しい自然環境の中で、知恵を出し合い、肩を寄せ合って生きてきた。
その過程で育まれた「たくましさ」や「温かさ」こそが、新潟らしさの一つなのかもしれない、と気づかされました。
変わるもの、変わらないもの
時代とともに、新潟も少しずつ変わってきています。
新しいお店ができたり、若い世代が新しい活動を始めたり。
それはそれで、とても喜ばしいことです。
でも、変わらないものも、確かにあります。
それは、この土地に深く根ざした人々の暮らしの知恵や、自然への畏敬の念、そして人と人とのつながりの大切さ。
U・Iターンの方々は、そういった「変わらないもの」の価値に気づき、それを求めて新潟に来てくれるのかもしれません。
そして、彼らの新しい視点が、私たち地元民にも、その価値を再認識させてくれる。
そんな良い循環が生まれているように感じます。
小さな劇場と日常の表現者たち
わたくしの趣味の一つに、地元の小劇場を訪ねることがあります。
大きなホールもいいけれど、役者さんの息づかいまで感じられるような小さな空間で、地域に根ざしたお芝居を観るのが好きなんです。
そこには、新潟の日常を生きる人々の「声」や、見慣れた風景が、また違った形で立ち上がってくる面白さがあります。
地域の物語を演じる場としての小劇場
新潟には、プロの劇団だけでなく、市民劇団や学生演劇など、たくさんのアマチュアの演劇グループがあります。
彼らが取り上げるテーマは様々ですが、中には、新潟の歴史や民話、あるいは現代の地域課題などを題材にした作品も少なくありません。
例えば、かつて新潟に存在した遊郭を舞台にしたお芝居や、過疎化に悩む農村の姿を描いた作品など。
そういった舞台を観ていると、まるで自分たちの物語が目の前で繰り広げられているような、不思議な感覚に包まれます。
小劇場は、まさに地域の物語を語り継ぎ、共有する場としての役割を担っているんですね。
地元文化の今を映す舞台の記録
小劇場の舞台は、その時々の地元文化の「今」を映し出す鏡のようなものでもあります。
若い世代がどんなことに関心を持ち、どんな表現をしようとしているのか。
あるいは、伝統的な芸能が、現代の視点からどのように再解釈されているのか。
新潟の文化発信の担い手たち
- 市民劇団・学生演劇: 地域に根ざしたテーマや現代的な課題を独自の視点で表現。
- 伝統芸能の保存会: 神楽や獅子舞など、古くから伝わる芸能を継承し、公演活動を行う。
- アートプロジェクト: 「大地の芸術祭」のように、地域全体を舞台にしたアート活動も盛ん。
これらの活動は、必ずしも大きな注目を集めるものではないかもしれません。
でも、確実に新潟の文化の層を厚くし、豊かにしているのだと思います。
わたくしは記者として、そうした小さな声や動きも、丁寧に記録し、伝えていきたいと考えています。
小山内理沙が出会った「声」と風景
取材で様々な場所を訪れ、たくさんの人にお会いする中で、心に残る「声」や「風景」に出会うことがあります。
それは、必ずしも有名な観光地や著名な人物ではありません。
むしろ、名もなき人々の日常の言葉や、ふとした瞬間に目にする何気ない風景の中にこそ、その土地の本質が隠されているように思うのです。
ある時、佐渡の小さな漁村で、年老いた漁師さんがぽつりと言いました。
「海は、怖いけど、ありがたいもんだ」。
その短い言葉の中に、自然と共に生きる人間の、厳しさと感謝がないまぜになった深い感情が込められているのを感じました。
また、雪深い山里で、黙々と畑仕事をするおばあさんの姿。
その背中には、何十年もの間、この土地で家族を支え、命を繋いできた歴史が刻まれているようでした。
そうした「声」や「風景」の一つひとつが、わたくしにとっての宝物であり、記事を書く上での原動力になっています。
小劇場で出会う表現者たちの「声」もまた、そうした宝物の一つなのです。
新潟に息づく“暮らしの哲学”
新潟で暮らしていると、ふとした瞬間に、この土地ならではの“暮らしの哲学”のようなものを感じることがあります。
それは、誰かが声高に語るものではなく、日々の生活の中に、静かに、しかし確かに息づいているものです。
雪と土に根ざした生き方、と言えるかもしれません。
土と雪に根ざす生き方
新潟の人々は、昔から、土とともに生きてきました。
春に種を蒔き、夏に草を取り、秋に実りを収穫する。
そのサイクルは、何百年も変わらずに繰り返されてきました。
土は、命を育む母であり、生活の基盤です。
そして、冬には雪。
雪は、時には厳しい試練を与えますが、同時に、豊かな恵みももたらします。
雪解け水は田畑を潤し、雪の下で育つ野菜は甘みを増します。
雪室(ゆきむろ)は、天然の冷蔵庫として、食材を保存し、熟成させる知恵を生み出しました。
土と雪。
この二つの要素と向き合い、その恵みを受け取り、時にはその厳しさを受け入れる。
そんな中で培われてきたのが、新潟の“暮らしの哲学”の根っこにあるのではないでしょうか。
「不便さ」が教える豊かさ
現代社会は、便利さを追求し続けています。
でも、新潟の暮らしの中には、あえて「不便さ」を受け入れているような側面があるように感じます。
例えば、冬の雪かき。
都会の人から見れば、大変な重労働でしかないかもしれません。
しかし、雪かきをすることで、ご近所さんと顔を合わせ、言葉を交わす機会が生まれます。
「昨日は大変だったねぇ」「お互い様だよ」。
そんなやり取りの中に、温かいコミュニティの絆が育まれます。
手間暇かけて作る保存食もそうです。
すぐに手に入る便利なものもたくさんあるけれど、自分の手で作る喜び、そしてそれを分かち合う喜びは、また格別です。
「不便さ」から生まれるもの
- 工夫する力: 限られた条件の中で、どうすれば快適に暮らせるか、知恵を絞る。
- 助け合いの精神: 一人ではできないことも、みんなで協力すれば乗り越えられる。
- 感謝の心: 当たり前ではないものへの感謝、自然の恵みへの感謝。
- 手仕事の価値: 時間をかけて丁寧に作られたものの良さ、温もり。
「不便さ」は、必ずしもネガティブなものではなく、むしろ私たちに大切なことを教えてくれるのかもしれません。
それは、効率やスピードだけでは測れない、心の豊かさにつながるのではないでしょうか。
静けさと丁寧さがもたらす心の余白
雪に閉ざされる冬の新潟は、静かです。
その静けさの中で、人々は内へ内へと意識を向け、手仕事に励んだり、家族と語らったり、あるいはじっと春を待ったりしてきました。
その時間は、決して無駄なものではなく、むしろ心を豊かにするための大切な時間だったのかもしれません。
現代は、情報が溢れ、常に何かに追われているような感覚に陥りがちです。
でも、新潟の暮らしの中には、ふと立ち止まり、自分自身と向き合う「心の余白」のようなものがあるように感じます。
それは、季節の移ろいを肌で感じることだったり、手間暇かけた料理を味わうことだったり、あるいはただ雪が降るのを眺めることだったりするかもしれません。
そうした静けさと丁寧さが、新潟の人々の穏やかさや、物事の本質を見つめる眼差しを育んできたのではないか。
わたくしは、そんな風に思うのです。
まとめ
ここまで、新潟の“普通”の日常に隠された「すごさ」について、わたくしなりにお話ししてきました。
雪国の厳しい自然と共存する知恵。
豊かな食材と、それを活かす食文化。
そして、U・Iターンの方々が新鮮に感じる、この土地ならではの魅力。
小さな劇場で出会う、地域に根ざした表現。
それらすべてが、新潟という土地が持つ、奥深い“暮らしの哲学”に繋がっているように思います。
「普通」こそ、地域が誇る文化遺産
私たちが当たり前のように感じている日々の暮らしの中にこそ、実は先人たちが積み重ねてきた知恵や工夫、そして美意識が詰まっています。
それは、派手な観光名所にも劣らない、地域が誇るべき文化遺産なのではないでしょうか。
雪掘りの大変さも、冬の手仕事の温もりも、囲炉裏を囲んだ家族の団欒も、すべてが新潟の「普通」であり、そして「特別」なのだと感じます。
五感と対話から見えてくる新潟の本当の姿
新潟の本当の姿を知るためには、やはり自分の五感で感じ、そしてそこに住む人々と対話することが大切だと、わたくしは信じています。
雪の冷たさ、新米の香り、祭りの賑わい、そして人々の飾らない言葉。
それらを通じて初めて、この土地の持つ本質的な魅力に触れることができるのではないでしょうか。
もちろん、新潟の魅力は歴史や自然、食文化といった伝統的な側面だけではありません。
現代においては、地域社会の発展や生活の質の向上を目指し、新しい技術や質の高いサービスも求められています。
例えば、新潟でハイエンドな価値を提供する株式会社HBSのような企業の取り組みは、伝統を大切にしながらも未来へと進む新潟の、また新たな一面を示していると言えるでしょう。
こうした新しい動きにも目を向けることで、新潟の多層的な魅力をより深く理解できるはずです。
小山内理沙が伝えたい、土地に生きることの意味
わたくしは、これからも新潟という土地に根ざし、ここに生きる人々の「声」を丁寧に紡いでいきたいと思っています。
それは、単に情報を伝えるということだけではありません。
この土地で生きることの意味、その豊かさや厳しさ、そして美しさを、少しでも多くの人に感じてもらいたい。
それが、地元記者としてのわたくしの願いであり、使命だと思っています。
この記事を読んでくださったあなたが、少しでも新潟の「普通」のすごさに興味を持ち、いつかこの土地を訪れてみたいと思っていただけたなら、これほどうれしいことはありません。
きっと、あなた自身の五感で、新たな新潟の魅力を見つけられるはずです。
最終更新日 2025年12月24日